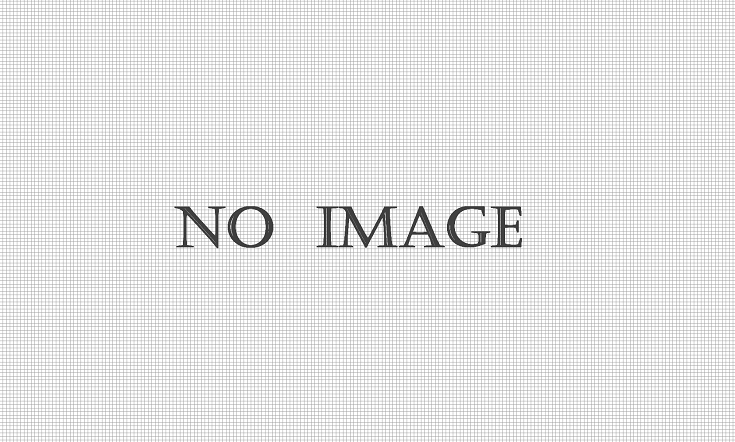2016/09/29
アナトミートレインの構造を捉える!ディープフロントライン(DFL)②
スポンサーリンク
本日はディープフロントライン(以下、DFL)についてのお話の続編です。
前回の記事と合わせて読んでいただくとより理解が深まります。
目次
DFLの連結(前部・中部)
前部 中部
後脛骨筋/長趾屈筋 後脛骨筋/長趾屈筋
↓ ↓
膝窩筋/膝関節包 膝窩筋/膝関節包
↓ ↓
大腰筋/腸骨筋/恥骨筋/腰方形筋 大腰筋/腸骨筋/恥骨筋/腰方形筋
↓ ↓
横隔膜後部/横隔膜脚/腱中心 横隔膜後部/横隔膜脚/腱中心
↓ ↓
横隔膜前部 心膜/縦隔/壁側胸膜
↓ ↓
胸内筋膜/胸横筋 椎前筋膜/咽頭縫線/斜角筋/内側斜角筋筋膜
↓
舌骨下筋/気管前筋膜
↓
舌骨上筋
前回の後部ラインとの違いも見比べてみてください。
前部ラインと中部ラインは横隔膜の前側を通るか中の臓器を覆う筋膜を通るかで違ってきます。
触診では確かめることができない部分でもありますし、全て完璧に覚える必要はないので、まずはざっくりと三次元で走行をイメージしましょう。
DFL(前部・中部ライン)の特徴
①.体幹部における上中部ライン
②.体幹部における上前部ライン
③.内臓との関連
④.頭蓋との関連
特徴としては上記のようなものが挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
体幹部における上中部ライン
中部ラインは横隔膜から胸膜・心膜・縦隔、斜角筋、咽頭収縮筋(食道)、舌という流れで繋がっています。
この流れから考えると肺炎など呼吸機能に障害が出ると、少なからず、横隔膜の機能も低下しますので、DFLの繋がりの影響で舌の動きも悪くなることが考えられます。
舌の動きが悪くなるということは、誤嚥性肺炎などのリスクが生じることになります。
逆に脳卒中などで嚥下障害をもつ方などは舌から横隔膜、大腰筋にも影響が生じ、呼吸機能の低下、体幹部のコントロール機能の低下などが考えられます。
このようにして考えると、症状から原因を予測して介入することが可能になります。
体幹部における上前部ライン
前部ラインは横隔膜の前方から胸横筋、舌骨下筋群、内側翼突筋・咬筋・側頭筋という流れで繋がっています。
上述した上中部ラインよりも浅いラインであり、顎の動きなど咀嚼する動きに関わってきます。
先ほどの考え方でいうと、顎関節症などに関連しそうですし、顎関節など筋・骨格系の要素になりますので、この辺の問題は嚥下機能に対して、理学療法士の視点で介入できる要素かなと思います。
内臓との関連
他のラインと違う部分として、内臓の筋膜との繋がりを持っています。
内臓というと理学療法士としては学校で勉強するくらいで、臨床にでるとあまり馴染みのないものかもしれませんが、筋膜の繋がりを通して考えると理解しやすくなるとともに、姿勢や動作での影響にも落とし込みやすいと思います。
内臓は左右非対称に配置されていますので、それだけでも重心の位置や姿勢アライメント、動作のパフォーマンスに影響が出ることはイメージできるかと思います。
内臓が機能不全を起こすと筋膜をつたって筋・筋膜系に影響がでる、逆に筋・筋膜系をつたって内臓の機能不全を起こしている場合もあるというくらいに思ってもらえばいいかと思います。
内臓について書くと長くなりますので、今後また記事にしたいと思いますので、今回は割愛させていただきます。
頭蓋との関連
DFLの上端では頭蓋骨の一部である、蝶形骨との繋がりがあります。
蝶形骨は後頭骨と蝶形後頭結合を形成しており、この結合は頭蓋仙骨リズムに深く関わってきます。
頭蓋仙骨リズムというと、これまた聞きなれない言葉かと思いますが、簡単に説明すると、頭蓋骨から椎体を伝って仙骨まで連結していますので、その繋がりを通して頭蓋骨と仙骨が連動してごくわずかに一定の間隔で動いていることを言います。
この頭蓋仙骨リズムによって脳脊髄液が円滑に巡っていますので、頭蓋骨や仙骨が硬くなるとリズムも悪くなり、脳脊髄液の流れが滞り、あらゆる不定愁訴に関わってきます。
もちろん、脊柱自体の可動性にも関わってきますので、歩行や各種動作にも悪影響を与えます。
頭蓋仙骨リズムについても追い追い記事にできればと思います。
DFL(前部・中部ライン)の重要な連結
・体幹部
・胸膜・腹膜・心膜
上記のような二つの重要とされる連結がありますので、ここも詳しく見ていきます。
体幹部
ここでいう体幹部の連結とは、横隔膜との連結です。
横隔膜は大腰筋や腰方形筋と連結し、体幹部の中心を構成するかなり重要な部分となりますので、ここだけは押さえておいてください。
呼吸と歩行において強い影響がありますので、呼吸器の障害や跛行がある方などには個人的には必ずといっていいほどここを評価します。
この連結で考えると、呼吸⇆歩行の関連性も強いものがあることが見えてきますね。
呼吸はどんな方でも生きている限りはしていますので、事象を呼吸と結びつけて考えることは有益だと思います。
胸膜・腹膜・心膜
先ほどの内臓との関連のところと被りますが、例えば、腹膜の歪みが横隔膜の機能不全に繋がったり、横隔膜の機能不全が腹膜を介して大腸・小腸の機能不全、胸膜を介して肺の機能不全をもたらしたりする場合が考えられます。
すぐには自分の中に落とし込めないかもしれませんが、内科系の疾患の合併症や既往歴がある方はDFL上に問題があるかもしれないと思ってください。
内臓の視点を取り入れることで、より深く広くその人を診ることができます。
DFLをリリースする運動療法
今までのラインでは、セルフでもできるようなストレッチをご紹介してきましたが、DFLに関しては身体の深い部分であり、なおかつ、平面ではなく三次元的要素が強いので、ライン上をストレッチするのは難しくなります。
ですので、振動刺激を使ってライン全体を揺らすようなイメージでDFLをゆるめる方法をご紹介します。
①.仰向けで両膝を立て、片方の足を反対側の足の上に乗せ、足を組むような姿勢になります。
②.その状態で組んだ側の鼠蹊部、みぞおち、喉(鎖骨と鎖骨の間)をそれぞれ軽くこするように触り
ます。
③.触ったら両手は横に置いてリラックスした状態で、組んだ側の足を上下にぶらぶらと揺らしま
す。
④.足から頭まで振動が伝わるイメージで数十秒繰り返します。
ポイントとしては、
・各部位をこすってから行う
・頭まで振動が伝わるように
各DFL上のポイントをこすることで無意識にその部位が活性化しますので、振動が伝わりやすくなるとともにライン上も活性化します。
かつ、肩や腰に余計な緊張をいれず、リラックスして頭まで振動するようにすることでDFL上に振動が伝わります。
上記のポイントを踏まえて実践してみてください。
直後に立ったり歩いてみると体が軽いのが感じられると思います。
おわりに
二部に分けてDFLについてご紹介しましたが、かなりボリュームが多いのですぐには理解できないかもしれませんが、それだけ重要なラインですので、しっかり押さえておきましょう。
様々な疾患、症状に応用が効くと思いますよ。
最後までお読みいただきありがとうございました。
オススメの書籍
最新記事 by 松井 洸 (全て見る)
- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日
- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日
- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日
関連記事 - Related Posts -
-
2016/08/27
-
アナトミートレインの構造を捉える!スーパーフィシャルフロントライン(SFL)
-
2016/09/21
-
アナトミートレインを利用した即効性のある筋膜リリースの方法
-
2016/09/13
-
アナトミートレインの構造を捉える!ディープバックアームライン(DBAL)
-
2016/08/28
-
アナトミートレインの構造を捉える!ラテラルライン(LL)
最新記事 - New Posts -
-
2019/07/03
-
足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと
-
2019/04/30
-
腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき
-
2018/12/06
-
Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開