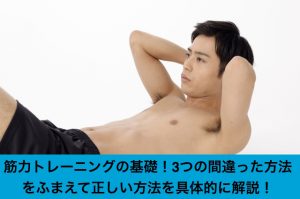2017/06/24
筋力トレーニングの基礎!3つの間違った方法をふまえて正しい方法を具体的に解説!

スポンサーリンク
この記事を書いている人 - WRITER -
なんとなく重りをつけて膝の伸ばしたり、なんとなく腹筋を10回など、指導していませんか?
本当にそれが歩行を始め、各種ADL動作の改善や痛みの軽減につながるのでしょうか?
なんとなくでは逆に悪化させてしまいかねませんよ!
私も新人の頃はそうでした。
しかし、周りの同僚、先輩がやっているから真似するのではなく、まず筋肉の基礎を理解した上で指導するべきです。
本記事では、筋肉の基本的な解剖学、生理学から筋力トレーニングをどう考えるべきなのか、リハビリに活かすにはどうしたらいいのかを分かりやすく解説していきます!
目次
筋力トレーニングの間違い
そもそも筋力トレーニング自体を間違った方法で指導しているかもしれません。
私の周りでは、評価もろくにせず、どんな疾患に対しても誰に対しても同じように、膝の屈伸運動や腹筋運動、足底から抵抗をかけてキッキングなど、ほとんどのセラピストがこのように指導しています。
もし、本当にこれが成り立つのであればセラピストじゃなくても誰が指導しても同じですよね。
紙に書いて渡して自主練習してもらっていいわけですよね。
「もっと筋力をつけないと良くなりません。」
「痛いのは筋トレが足りないからですよ。」
「歳だから仕方ありませんね。」
このような声も多く聞かれます。
教科書通りやっているのだから間違っていないと思うかもしれませんが、そもそも一人一人生活スタイルも違えば、骨格や動きの癖も違います。
教科書が間違っているわけではありませんが、教科書に誰でも当てはめようとすること自体に無理があります。
筋力トレーニングもそれ自体は決して悪くはありませんが、指導方法に問題があるのです。
以下に具体的に解説していきます。
筋力トレーニングの間違った指導方法
動作において単一の筋肉のみが働くことなんてことはまずありえません。
主動筋、拮抗筋の関係性や全身の関節が影響して動作が実行されます。
それなのに、単一の筋肉を狙ってひたすら反復運動をする。
何か矛盾を感じませんか?
本当に動作の改善を狙うならば、動作の中で筋肉が使えるように指導しなければいけません。
それを理解した上で単一の筋を狙ってトレーニングすべきと判断したのであれば良いと思います。
以下に間違った指導方法を解説していきます。
単一の筋肉のみの筋力トレーニング
大腿四頭筋なら座位で膝関節伸展に対して抵抗運動、あるいは下腿に重りをつける。
腹直筋なら背臥位から体幹、あるいは頭部を起こして収縮を促す。
これらの方法は、それぞれ筋肉が収縮する方向を考えて、抵抗を加えたり自動運動によって収縮を促していますよね。
しかし、これの方法はあることを無視したやり方です。
それは、そもそも私たちが立つ時、歩く時にこんな動き方はしないということ。
普段、生活の中で単一の筋肉だけを意識的に動かすなんて考えないですよね。
歩行のこのタイミングで中臀筋を収縮させて…脊柱起立筋で体幹を安定させて…なんて考えていたら生活するどころじゃありませんね。
私たちが普段、生活する際は複数の筋肉が共同で収縮したり、主動筋が収縮すると拮抗筋は弛緩するということを無意識におこなっています。
つまり、単一の筋肉のみを狙って意識的にトレーニングすることが、そのまま動作に活きてくるかというと別の話になります。
リハビリでは、歩行の自立ということが一つのゴールになることも多いかと思います。
歩行動作において、足関節、膝関節、股関節、脊柱、肩関節など全身の関節が連動した結果、「歩行」という動作が実現されます。
このことを考えても、単一の筋肉のみを狙ったトレーニング方法では全身の連動はできないでしょう。
メジャーな筋肉を鍛えることしか考えていない筋力トレーニング
このトレーニングはこの筋肉を鍛えるためのもの。
このような認識でトレーニングを指導していませんか?
あまり考えたことないかもしれませんが、「この筋肉はこの方法、あの筋肉はあの方法で…」というふうにそれぞれの筋肉に対してトレーニング方法を分けて考えているはずです。
しかし、上記の考え方でもやっぱり、筋肉の主動筋、拮抗筋などの関係性を無視した方法になってしまいます。
確かに、中臀筋なら股関節外転運動、下腿三頭筋ならカーフレイズというふうに動作によって優位に使われる筋肉はあります。
その筋肉のみを鍛えるという目的であれば、このトレーニング方法で間違っていないでしょう。
ですが、これでは優位に使われる筋肉しか働かず、他の筋肉との関係性を考えていません。
もし、このような方法で筋力トレーニングをするのならば、他の筋肉の関係性を考慮した上で指導するべきです。
上述したような全身の関節の連動を伴う方法がベストですね!
特定の肢位でおこなう筋力トレーニング
大腿四頭筋のトレーニングとしてパテラセッティング。
大臀筋のトレーニングとしてブリッジ運動。
上記の方法であれば、各筋肉に力を入れやすくピンポイントで鍛えることができるでしょう。
しかし、これも同様に日常生活でこのような肢位で力を入れる場面はありません。
同じ肢位での筋出力は上がるかもしれませんが、本来の目的とズレてしまいますよね。
リハビリでは、特定の肢位での筋力をつけることが目的ではなく、動作に活かすための要素の一つとして筋力をつけるという手段があるのです。
ブリッジ動作では床面に体幹が固定されているから大臀筋の収縮が入りやすいのであって、歩行場面で体幹の安定性を得た状態で大臀筋の収縮が同じように入るかというとそうではありません。
つまり、日常生活に直結するような動作で筋出力を発揮できるように指導する必要があるのです。
スポンサーリンク
筋力トレーニングの正しい指導方法
正しいという表現を使うと語弊があるかもしれませんが、目的によって正しい方法は変わってきます。
ボディビルダーのように筋肉隆々の体を目指しているなら、上記で挙げた方法で単一の筋肉を狙ってトレーニングすることは正しいと言えます。
リハビリの現場での筋力トレーニングは目的が違いますね。
ボディビルダーのような筋肉は求めていないので、元の生活に戻れるための一つの選択肢として筋力トレーニングという方法があるのです。
トレーニングを進めていくにあたって、MMTでは5レベルなのに歩行となるとうまく歩けない、こんな方もいらっしゃいますよね。
このような場合、どうしますか?それでも何も考えず筋力トレーニングを反復しますか?
筋力は十分あるのに動作に結びついていないということは、冒頭でも述べたように全身の連動が図れていないことが考えられます。
上記の例だけではなく、そもそもの筋力が弱いという方に対してもこれを意識したトレーニングを最初から取り組むことで、後からになって筋力は十分あるんだけど…ってことになりにくいです。
この全身の連動を図るために、ある基準を元に筋力トレーニングを指導します。
その基準とは、「インナーマッスルが働いた状態で実施する」ということです。
以下に詳しく解説しています。
インナーマッスルとアウターマッスルの関係性
筋肉には身体の深部、関節の近くに位置しているいわゆるインナーマッスルと表層に位置しているアウターマッスルの二つがあります。
インナーマッスルは、関節の近くに位置しているため、関節を動かすなどのダイナミックな働きはせず、関節の安定性に関与しています。
大腰筋、多裂筋、腹横筋などがあります。
反対にアウターマッスルは、関節をまたがって付着しているため、膝を伸ばす、肘を曲げるなどダイナミックな関節の動きに関与しています。
大腿四頭筋、上腕二頭筋、三角筋などがあります。
インナーマッスルによる関節の安定が図られているからこそ、アウターマッスルによってスムーズに関節が可動することができるのです。
インナーマッスルが働いていないと、関節の安定がないのでアウターマッスルで関節の安定と動きの両方を担う必要があります。
矛盾している二つを同時にすることに無理があるので、結果的に筋出力が低下する、痛みが出現するなどの症状に結びつくのです。
つまり、インナーマッスルが機能するとアウターマッスルは過剰な緊張をせず緩み、適切なタイミングで筋力を発揮しやすくなるという特性があるのです。
インナーマッスル筋のつながりディープフロントライン
全身のつながりを考える上で分かりやすい概念としてアナトミートレインというものがあります。
すごい流行ったので多くの人が知っているとは思いますが、知らないという方は以下の記事からどうぞ。
ざっくり言うと、筋膜でつながった筋肉同士がそれぞれ影響しあっており、極端な例だと足底から頭頂部までつながっているので足底の痛みが頭部筋膜の歪みが原因ということもありえなくはないのです。
そして、身体の中心を貫くインナーマッスルによる連結も存在しており、「ディープフロントライン」と呼ばれています。
詳しくは以下の記事をご参照ください。
上述したように、インナーマッスルを基準に筋力トレーニングすると良いのですが、このラインを基準に考えると全身との関係も考えやすいので便利ですね。
例えば、ディープフロントラインが機能していないと、拮抗するラテラルラインと呼ばれる身体の外側面を通るラインが過剰に緊張しやすく、筋力も発揮しにくくなりますし、硬く柔軟性に乏しくなることで痛みの原因にもなります。
これもインナーマッスル-アウターマッスルの関係と同様に考え、ディープフロントラインが機能しているからこそ表層の動きを作るラインが効率良く機能してくれます。
まとめ
・単一の筋肉だけを鍛えるトレーニング方法は動作に活きにくい
・特定の肢位でおこなうトレーニングはその肢位でしか効果が得られにくい
・インナーマッスルが働いているかどうかを基準に考える
おわりに
いかがでしたか?
あなたの周りにも間違ったやり方で指導しているセラピストの方いませんか?
明確な目的があるのならいいですが、何も考えずただ筋力トレーニングを反復しているだけでは時間がもったいないですし、効果も出にくいです。
本記事を読んで、まず、筋肉が効率よく働くためにはどうするのかという視点で考えるようにしてみてください。
ただなんとなく指導するよりずっと効果が出るはずですよ!
次回は上肢、下肢、体幹に分けてそれぞれ筋力トレーニングの方法を解説していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
オススメの書籍
The following two tabs change content below.


ロック好きな理学療法士。北陸でリハビリ業界を盛り上げようと奮闘中。セラピスト、一般の方へ向けてカラダの知識を発信中。
最新記事 by 松井 洸 (全て見る)
- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日
- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日
- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日
この記事を書いている人 - WRITER -
関連記事 - Related Posts -
-
2018/08/26
-
Physio365〜365日届ける理学療法マガジンnote〜
-
2017/10/14
-
膝蓋骨骨折のリハビリ【膝蓋骨の役割を最大限に引き出す重要なこと】
-
2017/11/17
-
パーキンソン病のリハビリ【特徴を理解すると対応の仕方もよく分かる】
-
2017/07/12
-
腰椎椎間板ヘルニアのリハビリ【痛みの原因から改善方法まで詳しく解説】
最新記事 - New Posts -
-
2019/07/03
-
足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと
-
2019/04/30
-
腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき
-
2018/12/06
-
Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開