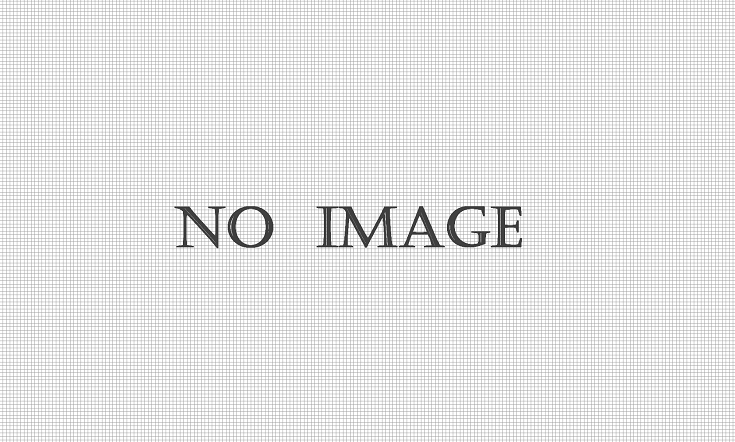2017/06/24
神経可塑性のメカニズムと脳卒中後の回復を最大限に引き出す3つの重大なポイント

スポンサーリンク
神経の可塑性を理解してリハビリしていますか?
脳卒中の回復において、神経可塑性は欠かせない要素の一つです。
きちんと理解することで、回復を最大限に引き出してリハビリすることができます。
これを理解しないまま脳卒中の方のリハビリにたずさわっていたと今改めて思うと非常に申し訳なく思います。
よく分かっていないかも…と思ったあなたは是非本記事を最後まで読むことをオススメします。
本記事には、神経可塑性のメカニズムと脳卒中回復過程に合わせたアプローチについて解説しています。
目次
神経可塑性とは?
そもそも神経可塑性とは何なのか?
残存した脳には脳損傷によって失われた機能を補うための適応する機能がある。
この機能のことを神経可塑性と呼び、神経回路を再構築して新たなネットワークを構築してくれる機能です。
この機能があるおかげで脳卒中後の機能回復が見込めます。
逆に言えば、この機能を如何に引き出すかでその後の回復度が変わってきます。
この神経回路の再構築はより強固にしたり、数を増やしたりすることもでき、セラピストが神経可塑性の原理を理解していることでこれに貢献できます。
一定期間を過ぎるとプラトーになってそれ以上の回復は見込めない。
確かに、一定期間を過ぎると急性期に比べて回復は緩やかに変化してきますが、新しい刺激を入力することで既存の回路がより強くなったり、今まであまり使用されていなかった回路が使われ始めたり、回路を再編成したりといった変化は起きています。
脳内には自身の身体、周囲の環境をどのように捉えるのか、これを地図として埋め込まれており、運動とそれによって得られる感覚入力を繰り返すことで新たな情報として脳内の地図が広がっていきます。
脳卒中後は、損傷した部位によって今まで処理されていたことを同様に処理できるように機能を変化させて適応しようとします。
これを「脳内地図の機能的拡大」と呼び、神経可塑性に伴って生じています。
これはここ20年くらいで言われ始めたことでまだまだ分かっていないことも多いかと思いますが、回復の終わりはないということを示唆しています。
そのためにもセラピストが正しく可塑性について理解して、不良姿勢のまま運動をおこなったり、動作に集中できるような環境設定などあらゆる要素にこだわるべきです。
そんな神経可塑性について以下に解説しています。
神経回復のメカニズム
神経損傷後はアンマスキング、側芽形成、神経細胞の移植によって回復されます。
神経細胞の移植に関しては、まだまだ一般的におこなわれるほど普及していないのが現状のため、今回はアンマスキングと側芽形成の二つについて解説します。
アンマスキング
アンマスキングとは、代償性の経路を構築することであり、元々存在していたがマスキング(抑制)されていたシナプスの結合が顕在化したものを指します。
例えば、シナプスA→シナプスBへCという経路で結合していたとします。
Cの経路が損傷された場合、シナプスAからシナプスBへの結合は途絶えることとなり、そこから先の運動機能は障害されます。
Cの経路を代償してDという経路を新たに構築し、その経路を使ってA→Bへの結合を再編成されることをアンマスキングと言います。
また、皮質脊髄路の内、85%は延髄で交差して下降しますが、残りの15%は通常では興奮しないようにマスキングされています。
脳卒中により、本来使用していた皮質脊髄路の経路が途絶えた場合、いつもは使用していなかった15%の経路を興奮させることで損傷された経路に代わって運動を起こすことが可能となります。
肩関節が屈曲できないのを肩甲帯の挙上や肘屈筋で代償してなんとか屈曲しようとするように、脳内でもなんとか代償して運動を発現しようとネットワークが再編成されるわけですね。
側芽形成
先ほどの例で言うと、シナプスA→シナプスBへCという経路で結合していたがCの経路が損傷されてしまった。
アンマスキングでは別の経路を使用しましたが、側芽形成では損傷された部分から再び経路をシナプスBへ伸ばして結合するというものです。
新たな経路を構築するというよりは、同じ経路を使用してシナプスの結合を再編成するというイメージです。
このような神経の可塑性があるおかげで脳卒中後の回復が期待できるわけですが、可塑性を促すためには刺激を入れ続ける必要があります。
適切な刺激が入ることで細胞間のやり取りがおこなわれますが、刺激がなくなると細胞間のやり取りがなくなり、細胞死を起こしてしまいます。(逆行変性)
細胞死が起こると再生はしなくなるため、麻痺の回復のチャンスを逃してしまわないためにもここはセラピストの関われる部分ですね。
運動麻痺回復ステージ
1st stage
半球間抑制
一次運動野の機能
1st stageの時期のアプローチ
スポンサーリンク
2nd stage
セラピストが意識すべきポイント
・セラピストと患者さんの間で目的、理想とする状態を共有する
・解剖、生理、運動学、動作分析などから実際の動作に必要な部分、足りない部分をフィードバックする
・実際の動作に対する患者さんのイメージ、イメージと動作でズレを感じていないか傾聴する
・必要に応じて徒手的に関節を操作、タッピング、触れることで感覚入力するなど、邪魔しない程度に足りない要素を補ってあげる
3rd stage
セラピストが意識すべきポイント
・現状に合った適切な課題の設定
・課題を過剰な努力を要せず実施できるための環境設定
運動麻痺の回復のためにセラピストが考えるべきこと
まとめ
・神経可塑性によって運動麻痺の改善が見込める
・麻痺側の不使用によって細胞死してしまうと回復は見込めなくなる
・1st stageでは皮質脊髄路の興奮に焦点を当てる
・2nd stageでは運動イメージと実際の運動との統合と修正をおこなっていく
・3rd stageでは日常生活で積極的に麻痺側を使えるよう環境設定する
おわりに
いかがでしたか?
回復過程に合わせて適切なアプローチを選択する重要性がお分かりいただけたと思います。
元の機能・能力を取り戻すためのリハビリなので、その回復を邪魔しないためにも神経可塑性のメカニズムは理解しておくべき要素の一つです。
明日からでも本記事の内容を参考にプログラムを設定してみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
出典・参考文献
1)原寛美:脳卒中運動麻痺回復可塑性理論とステージ理論に依拠したリハビリテーション.脳外誌.2012;21(7):516-526.
2)森岡周:神経可塑性と運動学習の脳内基盤.理学療法福井 13:3-9,2009
3)原寛美、吉尾雅春:脳卒中理学療法の理論と技術.2016
オススメの書籍
最新記事 by 松井 洸 (全て見る)
- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日
- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日
- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日
関連記事 - Related Posts -
-
2016/11/07
-
脳画像を読解する4つのポイント
-
2019/04/30
-
腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき
-
2016/08/30
-
アナトミートレインの構造を捉える!ディープフロントライン(DFL)
最新記事 - New Posts -
-
2019/07/03
-
足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと
-
2019/04/30
-
腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき
-
2018/12/06
-
Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開