2017/09/02
腰痛で立ち仕事が辛い方は必見!簡単すぎる3つの運動で腰痛撲滅!

スポンサーリンク
いつもお読みいただきありがとうございます!
理学療法士の松井です。
仕事柄立ち仕事が多い、家事で立ちっぱなしが多いなど立っている時間が長くて腰が痛くなった…という方多いですよね。
私も医療職のため、立ち仕事が多く、かがんだ状態でいることも多いので腰が痛くなることもあります。
しかし、あるポイントに気を付けて本記事でご紹介する運動も毎日実践しているので、痛くなってもその場だけで慢性的な腰痛になることはありません。
むしろ、痛くなることの方が少ないです。
腰痛で仕事や家事が満足にできないとそれだけでストレスですよね。
そんな方にこそ、是非本記事を最後まで読んでいただいてすぐに実践してほしいです!
目次
立っている時間が長くなるとなんで腰痛になるの?
そもそも、立ち時間が長くなるとなんで腰痛を発症してしまうのか。
以下にポイントをふまえて簡単に解説しています。
片方の足に偏って体重をかけている
ずっと立っていると、やはり疲れてきますので自然とどちらか片方の足に体重をかけてしまいますよね。
それが悪いわけではないですよ。
むしろ、ずっと真っ直ぐ直立している方が疲れると思いますので。
しかし、片方の足に偏って体重をかけているとデメリットもあります。
・外側の筋肉ばかり使うので、次第に疲れてきて負担になってしまう
・足の筋肉が疲れてくると、腰でかばうようになる
・腰でかばうと腰の筋肉が左右でバランスが悪くなる
ざっと挙げるとこんなところでしょうか。
上記のデメリットにならないように立つことができれば、片足に偏って体重をかけていても腰痛になるようなことはほぼありません。
順番に説明していくと、例えば右足に偏って体重をかけているとします。
この時、右太ももの外側からお尻にかけてパンパンに突っ張っていませんか?
太ももの外側からお尻の筋肉がピーンと突っ張ることで体を支えているからです。

筋肉には、伸びたり縮んだりすることのできる特徴があります。
ゴムをイメージしてもらうと分かりやすいんですが、ピーンと伸ばされたゴムは硬く指で突くと跳ね返すような弾力がありますね。
逆に縮んだゴムはふにゃふにゃで弾力はありません。
筋肉も伸ばされたゴムのように、ピーンと張ることで体を支えることができるのです。
ですが、伸ばされ続けたゴムはどうなりますか?
やがて伸びきってしまい、弾力はなくなってしまうどころかちぎれてしまうこともありますよね。
筋肉も同様に伸ばされ続けると、次第に力を発揮できなくなり、痛みが出ますし代わりに別の部分で力を出して体を支えようとします。
それがお尻のすぐ上にある「腰」にきてしまうので、腰痛を起こしやすいというわけなんです。
腰も太ももの例と同様に、左右どちらかの筋肉で体を支えようとします。
長時間、繰り返し左右どちらかの腰に負担がかかることで腰痛が慢性化してしまうのです。
腰が反っている
人は体の前で作業することの方が圧倒的に多いです。
つまり、前かがみになって作業しやすいということ。
具体的に言うと、胴体をみぞおち部分で上下に半分に分けて考えましょう。
手を使って作業するので、みぞおちから上は前のめりになります。
そのままだと前に倒れてしまうので、みぞおちから下はバランスをとって後ろに動かします。
つまり、腰を反らすことでみぞおちから上が前のめりになるのとバランスをとっているのです。
皆さんも自分の体でやってみてください。
写真のように、みぞおちから上部分を前に倒して手を伸ばしてみてください。
おそらく、遠くに手を伸ばすほどバランスをとるのが難しく、疲れるはず。

今度は、腰を反らした状態で前のめりになって手を伸ばしてみてください。
この状態だと腰が疲れてきませんか?
普段このように極端な姿勢はとらないかもしれませんが、少なからずこのようにして腰に負担がかかり、次第に腰痛になってしまうのです。

腰を反らすには、いわゆる背筋が力を発揮することで可能です。
しかし、ずっと腰を反らした状態だと背筋もずっと力を入れておく必要があるので、疲れてしまい次第に痛みに発展してしまうというわけです。
体をひねることが難しい
腰痛持ちの方は体をひねることが難しい場合が多いです。
では、ここで自分がどれくらい体をひねることができるのかチェックしてみてください。
痛みが強い方は無理してやらないでください。
ひねる際も急激に動かさず、ゆっくりと。
写真のように、座った状態で両手を胸の前で組み、後ろを振り向くように左右チェックしてください。
どうですか?後ろがしっかり見えていますか?

今度は、胸の真ん中から体を捻るように後ろを振り向いてみてください。
先ほどと比べてどうですか?振り向きやすくなっていませんか?
腰の痛みや突っ張り感が減っていませんか?

本来、体をひねる動きは腰ではなく、背中の背骨が動くからできるのですが、背中部分の背骨の動きが悪くて腰で無理やりひねっている方が多いです。
腰はひねる動きではなく、体を前に倒したり後ろに反らしたりする部分なので、ひねる動きを腰でやってしまうと簡単に痛めてしまうのです。
先ほど、胸の真ん中からひねるようにするとやりやすかったのは、背中の背骨でひねるようにしたからです。
仕事や家事をしていても、ずっと前を向いて作業しているわけではなく、体をひねって横や後ろの物をとったりしますよね。
そういった動きが次第に腰に負担をかける原因となっているのです。
スポンサーリンク
腰痛を引き起こす3つのポイント
ここまでの内容をまとめると、以下の3つのポイントが腰痛を起こす要因になりやすいです。
腰痛を起こす3つのポイント
・太ももの外側~お尻にかけての筋肉が伸ばされ、太ももの内側が縮んでいる
・腰が反った状態が続き、背筋が常に力を入れっぱなし
・背中ではなく、腰で体をひねっている
では、これらの3つのポイントを解消するための運動を以下にご紹介します!
股関節の運動
太ももの外側がピーンと伸ばされて内側が縮んでいる状態とは、言い換えると外側と内側の筋肉がバランスをとれていないということ。
本来は、バランス良く縮んだり伸びたりすることで、どちらかが過剰に伸びたり縮んだりすることはないのです。
要するに、内側も外側もバランス良く働かせましょうということで、股関節の動きを担う太ももからお尻の筋肉に対して、股関節を動かしてバランスを整えます。
1.肩幅に足を開いて立つ
2.鼠径部(ビキニラインの真ん中)をおさえる
3.おさえつつ、お尻を後ろに突き出して体を前に倒す
4.5~10回程度繰り返す
ポイント
・膝が足より前に出ないように、逆に伸びすぎないように軽く膝を曲げた状態を保つ
・体を倒したときに内ももが突っ張る感じがあればOK
・急激に動かさず、ゆっくりと動かす

背筋をゆるめる運動
常に背筋が緊張した状態をなんとかするには、緊張している背筋をほぐす、かつ、背筋が緊張しないように別の筋肉を働かせる。
この別の筋肉というのが、腰の背骨の前についている「大腰筋」という筋肉です。
いわゆる、インナーマッスルというもので腰のインナーマッスルである大腰筋がしっかり働けば、表面にある背筋は余計な緊張をしないという関係にあるので、それを利用します。
1.座った状態でみぞおちを軽くおさえる
2.おさえたまま、体を前後に曲げ伸ばし、左右に倒す、左右にひねる
3.それぞれ5~10回程度する
ポイント
・急激に動かさず、ゆっくりと動かす
・ひねる時は胸の真ん中からひねるようにする
・みぞおちには大腰筋を含む、複数の筋肉が重なっているので同時に刺激しつつ運動することができる
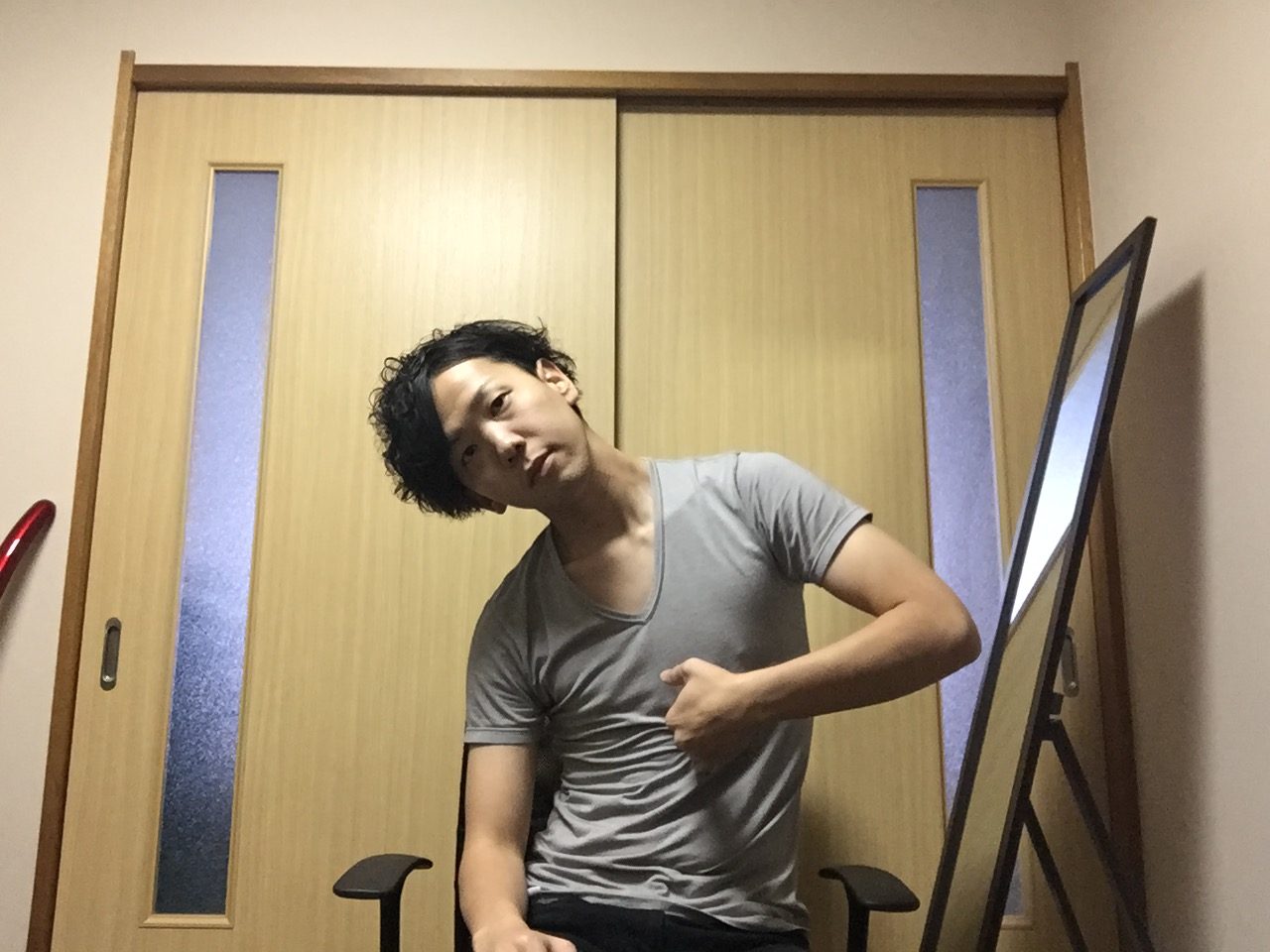
背中をひねる運動
背中ではなく、腰で体をひねっていることが腰痛を起こす原因の一つと言いました。
なので、シンプルに腰を動かさずに背中でひねる運動をします。
1.目線は前に向ける
2.顔、腰は動かさずに背中(みぞおちから上、首から下)を動かすように体を左右へひねる
3.左右それぞれ5~10回程度する
ポイント
・前を向いたまま頭を動かさない
・膝が内に入ったりしないように、足は動かさない
・動かす前に背中の背骨を手で軽くさすって、その部分を動かすことをイメージする
・急激に動かさず、ゆっくりと動かす


まとめ
・片足に偏って体重をかける状態が続くと、太ももの外側と内側の筋肉のバランスが悪くなる
・体の前で作業する際、腰を反らしてしていると背筋に力が入った状態が慢性化しやすい
・背中ではなく、腰で体をひねると負担が大きい
おわりに
いかがでしたか?
仕事や家事の合間にも簡単にできる運動ですので、まずはコツコツ続けてみてくださいね!
続けると確実に体は変わってきますので!
最後までお読みいただきありがとうございました。
最新記事 by 松井 洸 (全て見る)
- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日
- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日
- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日
関連記事 - Related Posts -
-
2017/04/24
-
首の痛みはこれで解決!理学療法士が勧めるストレッチ6選!
-
2017/03/07
-
坐骨神経痛の原因と治し方を筋肉の特性から解説!
-
2016/11/27
-
膝の痛みならこの3つの運動で解決
-
2016/10/13
-
五十肩は3つのストレッチと運動で解消!
最新記事 - New Posts -
-
2019/07/03
-
足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと
-
2019/04/30
-
腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき
-
2018/12/06
-
Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開
