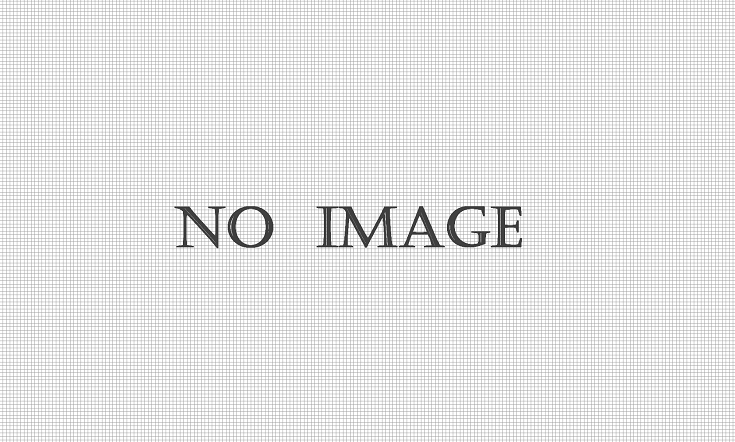2018/05/21
大腿骨頸部骨折のリハビリテーション【若手セラピストには是非読んでほしい】

スポンサーリンク
いつもお読みいただきありがとうございます!
リハ塾の松井です。
大腿骨頸部骨折は高齢者の3大骨折としても有名で、最も担当する機会が多いと言ってもいいくらい多い疾患の一つです。
新人セラピストの方でも一度くらいは担当した経験があるのではないでしょうか?
それだけ多く担当する疾患なだけに新人セラピストの方でも任されやすいですが、なんとなくリハビリしていても痛みが中々とれないという方も少なくはなく、股関節の構造を理解しておくことは必須と言えます。
本記事では、股関節の構造理解、頸部骨折後ではどの組織が影響を受けやすいか、可動域制限、筋力低下にはどの組織が関与しやすいか、急性期から退院までのリハビリの進め方について詳しく解説しています。
目次
大腿骨頸部骨折の概要
大腿骨の骨折は近位部から見て、骨頭、頸部、頸基部、転子部、転子下の順に骨折の部位ごとで名称が変わります。
頸部の骨折なら、大腿骨頸部骨折。
転子部の骨折なら、大腿骨転子部骨折というように。
これらの内、骨頭骨折と転子下骨折は交通事故や労働災害などによる高エネルギー損傷の結果、受傷することが多い。
頸部骨折、頸基部骨折、転子部骨折は高齢者の転倒など低エネルギー損傷の結果、受傷することが多いとされています。
関節包内骨折である頸部骨折と関節包外骨折である転子部骨折では、解剖学的な位置、血行動態的な血流の関係、運動学的なストレスのかかりやすさなどが違っており、骨癒合率などに差が生じ、術式も変わります。
関節包内骨折である大腿骨頸部骨折では、血液循環に乏しく骨癒合が得られにくいという特徴があるため、人工骨頭置換術が選択される場合が多いです。
関節包外骨折である大腿骨転子部骨折では、血液循環が良好で骨癒合が得られやすいという特徴があるため、骨接合術が選択される場合が多くなります。
大腿骨頸部骨折の発生数
2007年の大腿骨頸部骨折/転子部骨折の年間発生数は約15万人。
年齢別では、40歳から増加傾向で70歳を過ぎると急激に増加する傾向にあります。
このまま受傷者が増加していくと仮定すると、2020年には約25万人、2030年には約30万人、2042年には約32万人の大腿骨頸部骨折/転子部骨折の受傷者が増えていくとされています。
現状でもリハビリで担当する患者さんでは、大腿骨頸部骨折や転子部骨折の方が非常に多いですが、さらに増加していくことが予測されるということは、それだけ担当する機会も増えるかもしれないということで、セラピスト側の大腿骨頸部骨折に関する知識や股関節の解剖学や運動学的な知識は必須であると言えます。
男女比では、1:4で男性より女性が圧倒的に多いという結果でした。
閉経後の著しい骨密度の低下によるものと考えられています。
大腿骨頸部骨折の分類
頸部骨折の分類はGarden stageが有名ですね。
転位の程度により、以下のようなstageⅠ~Ⅳの4段階に分類しています。
| stageⅠ | 不完全骨折 | 転位なし | ヴァイトブレヒト支帯連続 |
| stageⅡ | 完全骨折 | 転位なし | ヴァイトブレヒト支帯連続 |
|
stageⅢ |
完全骨折 | 転位あり | ヴァイトブレヒト支帯連続 |
| stageⅣ | 完全骨折 | 転位あり | ヴァイトブレヒト支帯断裂 |
上述したように、関節包内骨折では人工骨頭置換術、関節包外骨折では骨接合術が選択される場合が多いということでした。
Garden stageでみると、関節包内骨折であってもstageⅠ、Ⅱで保存療法で治癒が見込めると判断された場合には骨接合術、または保存療法が適応となります。
骨頭への栄養血管の損傷の有無が骨癒合が得られるかどうかを決める要因になりますが、事前評価は困難であるため、転位がないstageⅠ、Ⅱと転位があるstageⅢ、Ⅳというように、転位の有無で判断されます。
大腿骨頸部骨折に対する手術療法
手術療法では、上述したように人工骨頭置換術もしくは骨接合術が選択されます。
ここで知っておくべきは術式はもちろんですが、どこから侵入して手術したか、ということ。
侵襲を受けた組織は当然、筋出力が低下しますし痛みが出現することも予測できます。
こういった事前情報を知っておくことで、痛みや可動域制限、筋力低下の原因についても仮説を立てやすいですね。
前方アプローチ
前方からの侵入では、大腿筋膜張筋と中殿筋の間から侵入します。
【前方アプローチのメリット】
・軟部組織の侵襲が少なくて済む
・脱臼が起こりにくい
【前方アプローチのデメリット】
・手術の難易度が高く、医師の高い技術が必要
前方から侵入しているため、股関節伸展+外旋+内転の複合運動で脱臼リスクを高めるため、注意が必要です。
後方アプローチ
後方からの侵入では、殿筋を切開して侵入します。
大殿筋、梨状筋を含む外旋筋を一旦大転子から切除。
軟部組織が損傷を受けるため、後方の支持性の低下につながります。
また、侵襲による影響もありますが、低下した支持性を高めるために筋緊張を高めている場合もあるので、安易に緊張を落とすようにストレッチやマッサージをするのは注意が必要です。
後方から侵入するため、股関節屈曲+内旋+内転の複合運動で脱臼リスクを高めるため、注意が必要です。
股関節の構造から考える大腿骨頸部骨折
前額面上には大腿骨長軸と頸部からなる、頸体角と呼ばれる約125°の角度が存在しています。
これが125°より小さいと内反股、大きいと外反股と呼ばれます。
内反股となって頸部が大腿骨長軸に対してより垂直に近づくと骨折しやすくなります。
以下、内反股の特徴です。
【内反股のメリット】
・股関節外転筋力のモーメントアームが増加
【内反股のデメリット】
・外転筋の機能的長さの減少
・大腿骨頸部にかかる剪断力の増加
さらに、大腿骨頸部/転子部骨折診療ガイドラインには以下のように記載されています。
【Grade B】
大腿骨頚部が長いことは大腿骨頚部/転子部骨折の危険因子である。
引用:大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン(改訂第2版)
*Grade A:十分な科学的根拠がある、Grade B:科学的根拠がある、Grade C:科学的に言い切れる根拠はない
つまり、大腿骨頸部が長いことが構造的に骨折リスクが高いと言え、内反股となるとさらに骨折リスクが増加することが言えます。
スポンサーリンク
大腿骨頸部骨折後のリハビリテーション
急性期(骨折後1~2週間程度)
この時期はまだ術後まもなく、手術で侵襲を受けた筋群が炎症を起こしている時期です。
ですので、過度な痛みを伴う運動や可動域を拡大しようと無理な関節可動域運動は炎症反応を助長する恐れがあるので注意が必要です。
多くは後方アプローチで殿筋群を切開していますので、侵襲による筋緊張の増加と股関節後方安定性を高めようと適応した結果としての筋緊張の増加が考えられます。
これによって、殿筋群は筋緊張が高く、痛みを訴える場合も多々あるかと思います。
しかし、ここで緊張を緩和しようとして安易にストレッチやマッサージを選択してはいけません。
まず、ストレッチによって切開した傷口が広がるようなことがあれば、当然痛いですしさらに緊張を高める、治癒が遅れるといったことが予測できます。
そもそも、股関節後方の安定性を高めようとした結果の殿筋群の筋緊張増加なので、緊張が緩和されたとしても股関節が不安定になってしまう、それによって痛みが出現することも予測できます。
この際に重要な考え方が、間接的に殿筋群を緩めるということ。
具体的には以下に記載してあります。
関節可動域運動
この時期は痛みが強い場合も多く、中々可動範囲を動かすことができないこともあります。
この時期に私がよく用いる手段としては、大腿骨遠位から骨頭に向けての反復押圧刺激です。
動かせる範囲だけ動かしてもいいのですが、やはり術後すぐに下肢を無造作に触られたり、動かされることには抵抗があるはず。
当然、変に力も入ってしまいますよね。
そんな時はクッションやセラピスト自身の足などを膝下や下腿の下に入れてリラックスできるポジショニングをしてあげること。
その上で、骨頭に向かって反復して軽く押圧刺激を加えます。
押圧刺激の反復でも関節内には動きが入るので、痛みを我慢してもらってまで無理に動かす必要はありません。
もちろん、痛みのない範囲で可動範囲を動かすことも必要ではありますよ。
私は両方をその方の状態を見つつ実施しています。
筋力トレーニング
上述した間接的に臀筋群を緩めるというのは、インナーマッスルの機能を高めるということ。
股関節のインナーマッスルは大腰筋があります。
大腰筋は骨頭を求心位に保つ作用があるので、股関節の安定性を高めることにつながります。
つまり、大腰筋によって股関節の安定性が得られたら、臀筋群の緊張を高めて安定性を得る必要がなくなるので、余計な力は抜けやすいということになります。
大腰筋に関して詳しくこちら↓
回復期(骨折後2〜6週間程度)
2週間もしたら炎症反応も落ち着いてきますので、痛みも術後まもなくよりは落ち着いているはず。
痛みに合わせて積極的に関節可動域運動、筋力トレーニング、歩行練習など進めていきます。
関節可動域運動
ADLの獲得に向けて可動域の獲得は必須ですが、背臥位で下肢を操作すると急性期と同様に痛みや防御性収縮によって思うように動かせない場合もあります。
このような場合は、急性期の時の反復押圧に加えて端座位での運動をオススメします。
下の写真のように手で鼠径部を触れてもらいつつ、体幹の前屈をします。
体幹の前屈でも相対的に股関節は屈曲位になりますよね。
臥位で緊張が高まってしまう方でも座位で自動運動ならそれほど緊張なくできる場合が多いです。
ポイント
・鼠径部をおさえることで股関節を支点にした運動となりやすい
・臥位に比べて下肢の緊張が抜けやすい
・股関節と骨盤、腰椎の連動した運動になっている

さらに詳しい関節可動域運動についてはこちら↓
筋力トレーニング
急性期と同様に大腰筋のトレーニングをしつつ、臀筋群のトレーニングも加えていきます。
何と言っても弱りやすいのが股関節の伸筋。
伸展筋が十分にあり、歩行時の適切なタイミングで出力できることで歩行中の推進力が得られます。
臀筋のトレーニングで大事なことは以下の記事にまとめてあります↓
歩行練習
徐々に離床を進め、病棟ADLの拡大を図る必要があるので歩行練習も必須ですよね。
跛行で多いのが、骨盤前傾位での歩行。
これは、股関節の安定性が不十分なために骨盤を前傾位とすることで骨頭被覆率を高めて安定性を作り出した結果。
つまり、まずは股関節の安定性を改善するべき。
股関節の安定性を無視したまま、「もっと体起こして。」、「胸を張って歩いて。」など言ったり徒手的に誘導しても一時的には良いかもしれませんが、すぐに元に戻ることが予測できます。
このためにも、重要なのが筋力トレーニングでもお伝えした大腰筋の働き。
大腰筋の働きがあるからこそ、股関節が安定して動くことができるし、可動性を出すこともできる。
これは必ず頭に入れておきましょう。
回復期〜退院(6〜8週間程度)
この時期は退院後の生活を想定してADL練習を積極的に実施します。
人工骨頭置換術を施行されている場合は、脱臼肢位について十分に本人、またはご家族に説明しておき、リハビリでの練習でも注意して取り組みましょう。
以下のポイントに注意しましょう。
もちろん、この時期だけではなく急性期からの指導も必要ですよ!
ADL上の注意点
・前方、後方どこからの侵入の手術か
・横座り時の肢位
・靴下、靴を履く祭の肢位
・ベッド上や畳などいざりして移動する場合の肢位や体の向き
・過屈曲となることはないか(低い座椅子に座ることがある、玄関で座って靴を履く際の上がり框の高さなど)
まとめ
・関節包内骨折は血液循環に乏しく骨癒合が得られにくい
・術式と前方、後方どちらからの侵入か確認するべき
・大腿骨は構造的に頸部が折れやすい構造となっている
・筋緊張が高い部分を安易に緩めることが良いとは限らない
・大腰筋の働きが股関節の安定性を高める
おわりに
いかがでしたか?
頸部骨折に限らず、股関節を診る上で大腰筋と股関節の基本的な構造の理解は必須です。
股関節疾患でなくても、歩行を考える上でも股関節はかなり重要であるので是非本記事を熟読していただきたいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考・引用文献
1.大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン(改訂第2版)
オススメの書籍
最新記事 by 松井 洸 (全て見る)
- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日
- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日
- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日
関連記事 - Related Posts -
-
2017/10/14
-
膝蓋骨骨折のリハビリ【膝蓋骨の役割を最大限に引き出す重要なこと】
-
2016/12/30
-
大腰筋のトレーニングを効果的にするための3つの役割
-
2017/10/03
-
腓骨遠位端骨折のリハビリ【足趾のトレーニングは各趾分けてするべき】
-
2017/07/05
-
圧迫骨折後のリハビリで最も重要なこととは?【一度潰れた椎体は元には戻りませんよ】
最新記事 - New Posts -
-
2019/07/03
-
足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと
-
2019/04/30
-
腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき
-
2018/12/06
-
Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開