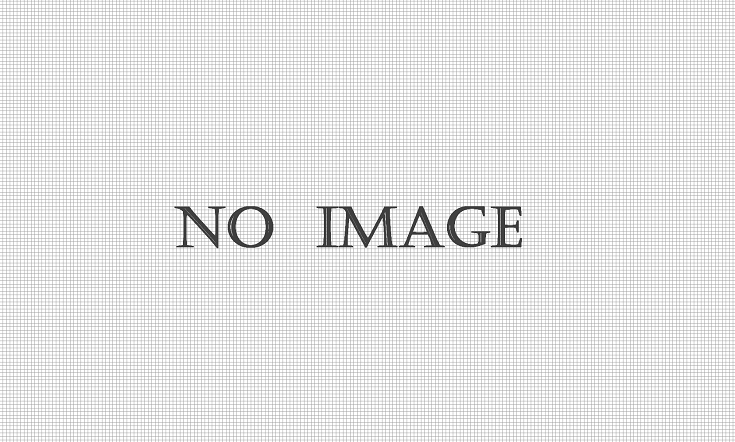2017/09/09
坐骨神経痛による症状を5つの原因から考える

スポンサーリンク
お尻から足にかけての痺れ、歩く時に力が入らない、痛くて座っていられないなどの症状を訴える方はいませんか?
目次
坐骨神経痛とは?
まず、そもそも坐骨神経痛とはどのような状態となっていることを指すのか理解しておきましょう!
坐骨神経痛とは、坐骨神経の分布域に放散する神経痛で、神経の走行に沿って疼痛を感じます。
坐骨神経の走行路に近接する腰椎下部の椎間板ヘルニアや腫瘍による神経の圧迫などで起こり、好発部位はL4〜S1の障害が多く認められます。
病院では、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症を疑って検査しても画像上はなにも原因がわからない場合があり、原因がはっきりしない臀部から足にかけての痛みのことを総称して坐骨神経痛として診断されることもあります。
また、手術によってヘルニアなどによる神経の圧迫は取り除かれているはずなのに症状が改善しないこともあります。
この場合、上記疾患の疑いはないので坐骨神経が走行している部位のどこかでなんらかの要因によって神経が障害されていることが考えられます。
筋肉の柔軟性低下、筋緊張増加による圧迫や筋肉同士の癒着、関節の可動性が悪いことで筋肉の動きが悪くなっている、または硬くなっていることで坐骨神経に対して刺激を与えており、坐骨神経痛様の症状が出ている可能性があります。
純粋にヘルニアなどによる神経の圧迫によって出現している症状なのか、それより遠位で筋肉など軟部組織由来による症状なのか、どちらも混在しているのか鑑別する必要があるということです。
軟部組織由来のものであれば、理学療法士によって改善できる可能性がありますからね!
坐骨神経痛の症状
代表的な症状としては、以下のような症状が挙げられます。
・腰、臀部、下肢(大腿、下腿、足部)の片側に痛みや痺れが出る
・座っていると上記部位に痛みが出る
・臀部から足にかけて力が入りにくい感じがする
・歩くと上記部位が痛い
痛みの部位、異常感覚、筋力低下が起きている部位と画像上認められている神経所見と一致していない場合は軟部組織由来の原因が考えられます。
坐骨神経の走行分布
坐骨神経は、脛骨神経と総腓骨神経が一つに束ねられたものです。
これら二つの神経は多くの場合、膝窩上部で脛骨神経部と総腓骨神経部にそれぞれ分岐します。
(高位分岐型:骨盤腔内で既にこの分岐が起きている 15〜20%の頻度で認められる)
脛骨神経は、そのまま下腿後面〜足底に分布。
総腓骨神経は、さらに浅腓骨神経と深腓骨神経に分かれ、下腿前面〜足背に分布します。
両者とも大腿後面にも分布しており、脛骨神経が大腿内側、総腓骨神経が大腿外側に分布しています。
さらに近位を見てみると、L4〜S3から出ている神経が合わさって坐骨神経となり、梨状筋下孔(梨状筋が大坐骨孔を上下二つに分けて出来る下の部分)を通り、そのまま下降しています。
ざっくり言えば、坐骨神経は大腿後面の筋、下腿と足部の全ての筋、および下腿と足部のほとんどの皮膚に分布している神経です。
スポンサーリンク
坐骨神経痛との類似疾患
梨状筋症候群
上述しましたが、梨状筋下孔と呼ばれる部位を坐骨神経が通過していますので、なんらかの原因で梨状筋によって坐骨神経が圧迫されると坐骨神経に沿った痛みを引き起こす可能性があります。
梨状筋は股関節外旋に作用する筋であり、深層に位置しており骨頭を求心位に保つ役割も担っています。
・深部筋のため、使われにくく廃用を起こし硬くなる
・仙腸関節、股関節の可動性低下により硬くなる
・大臀筋、中臀筋、小臀筋などとの癒着により硬くなる
上記の要因によって梨状筋が硬くなり、坐骨神経を圧迫してしまう可能性が考えられます。
仙腸関節障害
坐骨神経は近位を辿ると、脊椎から分布している神経が束になっています。
脊椎から出て、仙骨の前方から仙腸関節をまたいで梨状筋下孔を通過して大腿後面に出てきます。
例えば、仙骨が前屈(ニューテーション)しているとすると、坐骨神経は仙骨の前方を走行しているため、仙骨に押されて前方への伸張ストレスがかかることが考えられます。
このように、仙骨と寛骨の位置関係が崩れると近くを走行している坐骨神経も影響を受けやすいということが言えます。
腰椎椎間板ヘルニア
椎間板の内側にある髄核が繊維輪を飛び出し、後方にある神経根を刺激してしまうことで痛みを発生させます。
これは画像上で原因がはっきりとしているので、神経を刺激している部分が解消されると痛みは消失することになります。
坐骨神経痛を起こす要因
坐骨神経痛を引き起こす要因としては、坐骨神経の走行している部分をチェックします。
ヘルニアなど画像上問題がなければ、筋肉などによって神経の走行している部分の動きが悪くなっていることで発症している可能性があります。
腰椎の可動性低下
ヘルニアみたいに画像上明らかに問題があるとまではいかなくても、わずかなズレでも神経からの伝達は悪くなります。
そのズレによる直接的な症状はなくても、神経から筋肉へ送られる伝達が悪くなることによって筋発揮力が低下、筋肉の動きが悪くなる、運動パターンの変化、関節への影響などが起こり、二次的に坐骨神経領域に負担がかかり痛みとして出現することも考えられます。
ですので、明らかな問題がないから関係ないとせず、必ずチェックしておきましょう。
以下に原因となりうる筋群を挙げています。
・脊柱起立筋
・多裂筋
・広背筋
・腰方形筋
・大腰筋
・横隔膜
仙腸関節の可動性低下
これは上述しましたが、仙骨と寛骨の位置関係の崩れによって仙骨の前方を走行する坐骨神経にもストレスがかかる可能性があります。
仙腸関節がズレたまま固まったり、可動性が悪いことで必要以上に周囲の筋肉が働かなくてはならず、筋肉に過剰な負担がかかることで坐骨神経にストレスがかかると痛みが出現することが考えられます。
以下に原因となりうる筋群を挙げてあります。
・大臀筋
・中臀筋
・小臀筋
・梨状筋
・腸骨筋
・大腰筋
・腰方形筋
・腹直筋
・腹斜筋
・ハムストリングス
・内転筋群
細かく挙げるとまだありますが、長くなるのでここまでで。
股関節の可動性低下
痛みが出現するのは、大腿後面の股関節に作用する筋群なので当然股関節の可動性も影響します。
股関節の可動性が悪いと、股関節の筋群の柔軟性低下や筋同士の滑走性低下により神経の動きも悪くなることが考えられます。
また、坐骨神経は梨状筋の下を走行しており、梨状筋は股関節に停止を持ち、直接股関節に作用する筋肉であるため、股関節の可動性の悪さは梨状筋へも影響を与えます。
ポイントは、回旋制限の有無を評価してみると良いです。
筋肉による影響
坐骨神経の走行に沿った部分にある筋肉の柔軟性低下、筋肉同士の滑走性の低下があると直接神経を圧迫することもあるし、二次的に神経の動きが悪くなり慢性的なストレスで痛みが出現することも考えられます。
筋肉はバラバラに存在しているわけではなく、互いに重なるようにして位置しています。
関節運動に伴って、それぞれの筋肉が筋繊維の方向に沿って収縮や弛緩をしており、重なっている部分では互いに滑り合うようになっています。
しかし、筋肉が重なっている部分で炎症や廃用によって癒着が起こると、本来滑り合うことでスムーズに運動ができるはずが、滑らなくなることで色々な弊害が考えられます。
・筋肉同士が滑らないために過剰に筋収縮を起こす
・癒着が起こると本来筋肉が位置している場所からズレてしまい、正常な運動から逸脱する、本来負担がかからない組織に負
担をかけてしまう
・当然、神経と他組織とも滑りあう必要があるので神経にも負担がかかる
以下に坐骨神経領域で問題となりやすい部位を挙げています。
筋膜による影響
まとめ
おわりに
オススメの書籍
最新記事 by 松井 洸 (全て見る)
- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日
- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日
- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日
関連記事 - Related Posts -
-
2016/09/19
-
筋骨格系疼痛における筋膜リリースの実際
-
2016/12/30
-
大腰筋のトレーニングを効果的にするための3つの役割
-
2017/07/12
-
腰椎椎間板ヘルニアのリハビリ【痛みの原因から改善方法まで詳しく解説】
最新記事 - New Posts -
-
2019/07/03
-
足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと
-
2019/04/30
-
腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき
-
2018/12/06
-
Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開