2018/09/01
圧迫骨折後のリハビリで最も重要なこととは?【一度潰れた椎体は元には戻りませんよ】

スポンサーリンク
いつもお読みいただきありがとうございます!
リハ塾の松井です。
圧迫骨折は担当する機会が多い疾患の一つでもあるため、若手セラピストでも誰もが担当すると思います。
急性期では痛みが強いことが多く、あまり積極的にリハビリを進められずになんとなくマッサージや平行棒で起立練習や歩行練習をしていませんか?
痛みを訴える方に対して「コルセットをしっかり締めておきましょう!」、「なるべく腰を捻らないようしましょう!」などと、漠然とした指導をしていないでしょうか?
本記事では、なぜ圧迫骨折が起こるのか、病態理解、解剖・生理・運動学から考える構造的な問題と改善策をまとめてあります。
なんとなくのリハビリをするのは病態やなにがダメでなにが有効なのかわかっていないからです。
圧迫骨折について理解を深めて適切にリハビリを進められるようになりましょう!
目次
圧迫骨折のリハビリ目的
まずは目的を明確化しておくと、評価からアプローチまでの流れがスムーズになります。
具体的な目的としては以下の通り。
・腰部へストレスをかけない姿勢、動作の獲得
・痛みの軽減
・歩行などADLの再獲得
何らかの受傷起点があって骨折したとしても、腰部へ過剰なストレスとなるような姿勢や動作であると、骨癒合後も痛みが長引きやすい方が多いです。
流れとしては、歩行などの各種ADLの再獲得を長期的なゴールに置き、痛みの軽減を図りつつ腰部へストレスをかけないような姿勢や動作を指導、獲得していくという流れになります。
圧迫骨折とは?
そもそも圧迫骨折とはどのような状態を指すのか、簡単におさらいしましょう。
名前の通り、背骨が圧潰、潰れてしまう状態を指します。
圧迫骨折の有病率(陳旧性を含む)は60歳代で7~14%、70歳代で37~45%と70歳代の約半数が圧迫骨折を有している。
高齢者の2人に1人が圧迫骨折というかなり身近な疾患であり、リハビリで担当する機会もそれだけ多いわけですね。
原因としては、骨粗鬆症による骨密度の低下による要因が大きいです。
中でも、男性より女性の方が好発しやすく、閉経後のエストロゲンの低下が急激に骨密度を低下させてしまうからとされています。
女性で高齢といった条件があると、圧迫骨折が発生しやすいということですね。
また、圧迫骨折のリスクがあると思って予防に取り組むことも必要かもしれないということ。
好発部位としては、Th12~L1の胸腰椎移行部、次いでTh7~8の中位胸椎、腰椎という順に好発しやすいです。
胸腰椎移行部で好発しやすい理由としては、以下の通りです。
・脊柱の構造的に負荷がかかりやすい(移行部より上位では肋骨によって固定力が大きい、腰椎の可動性が大きい)
・回旋可動域が大きい胸椎と回旋に乏しい腰椎の境界であり、力学的な負荷がかかりやすい
・Th11~L2椎体が楔状型の前方凸の形状に圧潰変形しやすいため、脊柱後湾しやすい
・胸腰椎移行部では力学的に負担がかかりやすいこと、楔状変形が起こりやすいことから椎体の圧潰が進みやすい。
・圧潰が進むと脊柱の後湾も大きくなり、別の部位の圧迫骨折を起こしやすくなる。
・如何に椎体の圧潰を防ぐかがポイント!
圧迫骨折による痛み
主な症状はなんといっても「痛み」ですよね。
痛みを起こさないように気を付けつつ、椎体の圧潰を進行させないことが重要になります。
一般的に、痛み自体は1か月程度で治まり、3か月程度で約50%の骨が癒合、6か月程度で約80%の骨が癒合します。
ですので、痛みがないから大丈夫というわけではなく、痛みが消失した後も多くの場合は骨癒合が未完成であり、圧潰によって脊柱後湾、他の椎体の骨折リスクも増加します。
患者さん自身も痛みがなくなるとあまり患部に気を使わなくなる可能性もあるため、セラピスト側が圧潰のリスクを理解して動作指導や良肢位を含めたリハビリテーションを展開していくことが求められます。
・急性期の疼痛管理
・急性期からの椎体の圧潰予防
この二つの視点が特に重要。
圧迫骨折によるリスク
圧迫骨折後の患部の痛みの多くは1ヶ月程度で治まってくる傾向にあります。
受傷後1ヶ月以内の症例では、寝返りや起き上がり、移乗や歩行も痛みが強く満足にできないこともしばしばあります。
1ヶ月以上経過し、患部の痛みは落ち着いてくると臀部や大腿部など下肢の痛みを訴えることがあります。
脊柱は身体の中心を貫いているため、脊柱アライメントの変化によって上下肢に及ぼす影響は大きいためです。
運動連鎖を考えるとイメージしやすいですね。
このアライメント変化によって、偏ったストレスがかかる部位が出現し、患部以外に痛みを訴えることがあるということ。
また、稀に椎体後壁が圧潰することで脊柱管を圧迫し、脊柱管狭窄症や脊髄麻痺を引き起こすこともあります。
直接的な外傷ではなく、本当に二次的な症状であるなら単純に下肢をマッサージするだけでは改善が見込めない場合もあります。
一度、圧潰変形によって脊柱が後弯してしまうと元には戻りません。
二次的な症状を引き起こさないためにも、急性期からの圧潰の予防の視点が重要になるというわけですね。
また、圧迫骨折が一度起こると隣接椎体の骨折リスクが5倍程度高まるとされており、再骨折にも最新の注意を払うとともにリスクを十分に指導していくことも必要です。
圧迫骨折後の圧潰予防
圧潰を予防するには、圧潰するようなストレスがかかりやすい部位、ストレスがかかる姿勢、動作を理解しておくべきです。
圧潰が進行しやすい部位としては、やはり胸腰椎移行部のTh12~L1。
この部位は体幹の最大伸展位でも前弯位まではなりません。
つまり、常に後弯しており、椎体の前方に圧力がかかっているということ。
そのため、上述したように他の椎体より圧潰のリスクが高く、楔状の変形となりやすいのです。
ストレスがかかりやすい姿勢としては、やはり座位姿勢は脊柱起立筋が弱く体幹伸展位を保てない方では後弯方向にストレスがかかってしまい、圧潰を進行するリスクがあります。
背臥位では骨折部に重力による適度な圧縮力がかからず不安定な場合があり、そのような状態で脊柱起立筋を作用させ骨折部の離開力を働かせると骨折の治癒が遅延する可能性がある。
赤羽根良和:理学療法ジャーナル 44巻6号 骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折に対する運動療法の意義-椎体圧潰変形の抑止効果について
上記のような報告もあり、背臥位も骨折部にはリスクが高く、ギャッジアップ30°程度により適度な圧縮力を作る、あるいは側臥位がリスクが低いとされています。
ストレスのかかる動作としては、寝返り、起き上がり動作。
これは入院されてすぐに指導するべき動作ですね。痛くて動くどころじゃない場合もありますが。
普段、皆さんが寝返りする際は下肢または上肢が先行して回旋することがほとんどですよね。
しかし、これでは脊柱への回旋ストレスが大きいので、上下肢-体幹が一直線となったいわゆる丸太様の寝返りをするべきです。
これによって、骨折部の回旋ストレスを軽減することができます。
また、起き上がりに関しては寝返りで側臥位になった後、そのまま体幹を起こすと椎体には圧縮ストレスがかかりやすいです。
ですので、起き上がり時は一度腹臥位を経由してから片足ずつベッド下へ降ろし、高這いから立位となる流れが骨折部のストレスを最小限にするには推奨されます。
体幹をなるべく伸展位で保持したまま動作をおこなうということですね。
骨折部にストレスをかけないためには安静臥床がいいのかもしれませんが、臥床期間が長くなると高齢者では認知症のリスクも高まります。
骨癒合を邪魔しない範囲で離床を促していくことが必要になります。
骨癒合と認知症のリスクの双方を天秤にかけながらリハビリを進めなくはいけないということです。
大腰筋と脊柱の重要な関連性
大腰筋は股関節を屈曲させるだけでなく、脊柱を直立化してくれる作用も持っています。
圧迫骨折における大腰筋がうまく働いていないことのデメリットとしては以下のようになります。
・腹直筋、脊柱起立筋が過剰に収縮しやすく、骨折部にストレスとなる
・腹直筋が過剰に収縮すると腰椎は後弯して圧潰が進行しやすい
・股関節周囲筋も過剰に収縮しやすく、股関節の可動性が制限され、腰椎にストレスとなりやすい(股関節と腰椎に関しては以下に記述しています)
臨床でも私はまず、大腰筋を活性化させることに注力します。
その方が骨折部のストレスを減らすことにつながるし、その後の歩行もスムーズに進めることができる場合が多いからです。
大腰筋に関して詳しくはこちら。
圧迫骨折の評価
診断方法としては以下のようなものが挙げられます。
画像診断
レントゲン
レントゲンのメリットとしては、椎体の圧潰度合いを定量的に追うことが可能です。
しかし、急性期の新鮮骨折と陳旧性の骨折の区別が難しいことがデメリットとして挙げられます。
MRI
多くはMRIによる画像診断で診断がつきます。
新鮮骨折でははっきりと信号が出ていないこともあり、少し期間をあけてから再度撮るとはっきり見えることもあります。
骨折部にははっきりと信号変化が認められるので有効とされています。
圧迫骨折の治療法
治療法としては以下のようなものが挙げられます。
手術
多くは保存療法を選択されますが、以下に当てはまると手術が適応となります。
・椎体の圧潰率が50%以上
・20°以上の後弯変形がある
・脊髄、馬尾神経症状がある
・膀胱直腸障害がある
・椎体に不安定性がある
万が一、リハビリを進めていく中で神経症状や膀胱直腸障害の可能性が考えられたらすぐに主治医に確認してもらいましょう。
術式としては、椎体内にセメントを注入する(経皮的椎体形成術)、あるいは、周りの椎体を金具で固定するといった方法がとられます。
薬物療法
骨折後には以下のような薬剤が処方されている可能性があるので、患者さんが何を目的にどの薬を服薬しているのか把握しておきましょう。
・消炎鎮痛剤:ロキソニン、ボルタレン
・骨形成促進剤:フォルテオ、テリボン
・骨吸収抑制剤:ダイドロネル、ボナロン、ボノテオ、ベネット
スポンサーリンク
圧迫骨折後のリハビリテーション
急性期(骨折後1~2週間程度)
この時期は強い疼痛を伴う場合が多いため注意を払う必要があること、骨癒合を阻害しないことが重要となります。
基本的には安静が第一で、痛みと相談しながら可能な範囲で離床を促していきます。
安静姿勢としては以下が推奨されます。
・ギャッジアップ30°程度で背臥位
・側臥位
以下の姿勢、動作は骨折部の圧潰リスクが高まるので注意
・フラットなベッドでの背臥位
・端座位(取る場合は体幹伸展を促す)
・患部に回旋ストレスがかかる動作(寝返り、起き上がり)
運動療法
ベッドサイドで可能な範囲で運動療法も実施していく必要があります。
まず、考えるべきなのは骨折部の負担を軽減すること、椎体の安定性を高めること。
圧迫骨折が多い胸椎移行部で考えると、上下には胸郭・胸椎と股関節があります。
腰椎は構造的に回旋に乏しく、胸椎と股関節は回旋可動性が大きいです。
このことから、もし股関節、胸椎の可動性に制限があるとどうなると思いますか?
動作時には制限された胸椎、股関節を代償して腰椎に回旋ストレスがかかることが予測されます。
そのため、胸椎、股関節の可動性が低下しないように、制限が既にある場合は可動域の改善に努めることが骨折部のストレスを軽減することにつながります。
具体的には以下の通りです。
・上肢、肩甲帯周囲の軟部組織のマッサージ、ストレッチ
特に三角筋、僧帽筋が固まると肩甲帯、胸椎の制限につながるためしっかり柔軟性を引き出しましょう。
また、拮抗する広背筋、前鋸筋の柔軟性も引き出しておくと尚良いですね。
・上肢、肩甲帯のROMex
・下肢の軟部組織のマッサージ、ストレッチ
圧迫骨折の方は脊柱後弯が大きいアライメントを呈していることが多いです。
脊柱後弯による運動連鎖から、股関節屈曲・外転・外旋位、膝関節屈曲位となっていることが多いです。
股関節屈曲・外転・外旋筋(中臀筋、大臀筋、大腿筋膜張筋、大腿直筋)、膝関節屈曲筋(ハムストリングス、腓腹筋)の柔軟性を引き出しておきましょう。
また、拮抗する股関節伸展・内転筋(大内転筋、長内転筋、ハムストリングス)、膝関節伸展筋(内側広筋)の柔軟性も引き出しておきます。
・下肢のROMex
・筋力トレーニング
骨折部に負担がない範囲で筋収縮を促します。
上記のように、脊柱後弯、股関節屈曲・外転・外旋、膝関節屈曲位のアライメントと拮抗する筋の収縮を促していくと良いですね。
<筋収縮を促しておくと良い筋肉>
・上肢
前鋸筋、広背筋
・下肢
内転筋群、ハムストリングス、大腰筋、腸骨筋、内側広筋
オススメの下肢トレーニング
1.片方の膝の上に反対側の下腿をのせる
2.股関節屈曲・外旋方向へ動かす
大腰筋を狙って筋収縮を促せます。
ポイントは、ゆっくりと可能な範囲で大きく動かしてもらうこと。
回復期(2~4週間程度)
この時期はある程度痛みは落ち着いてきますが、骨癒合が完全にできているわけではないので注意は継続して必要です。
急性期より動けるようになっているはずですので、離床を急性期より積極的に促していきます。
<離床時のポイント>
1.側臥位から腹臥位となる
2.腹臥位から片足ずつベットから降ろす
3.高這いとなってから立位となる
腹臥位をとれない方も多いので、必要に応じて介助してあげることが望ましいです。
ADLも徐々に拡大していく必要があります。
整容動作、更衣動作など立位で可能なものは立位で体幹伸展位としておこなうことが望ましいです。
もちろん、ケースバイケースで立位が転倒リスクがある方は無理に勧めず、他職種と連携を取りながら進めましょう。
運動療法
この時期は歩行練習を中心に圧潰を予防する意味で立位で進めることが望ましいです。
骨折部の痛みに応じてですが。
具体的には以下の通りです。急性期から加えたものを記載してあります。
・歩行練習
体幹が過度に屈曲位とならないように促しつつ、適切な歩行補助具を選択してあげましょう。
・上肢の筋力トレーニング
棒体操などで体幹伸展を伴って広背筋の収縮を促していきます。
可能なら立位で。
ポイントは、肩甲帯が挙上しないように肩甲帯下制を意識して。
・下肢の筋力トレーニング
大腰筋、内転筋群の収縮を積極的に促していきます。
1.肩幅に足を開く
2.鼠蹊部を触れる
3.そこを支点に体幹を前傾、臀部を後方に引く
<ポイント>
・膝関節が足部より前に出ない、過伸展しないように
・体幹を伸展位に保つ
立位が難しい場合、以下の写真のように体幹伸展位を保持しながら座位でも可能です。
前方に支持物を置き、両手で支持して実施しても良いですね。
回復期〜退院〜退院後(4~8週間程度)
この時期であっても骨癒合はまだ8割くらいです。
ですので、退院後にも圧潰を進行させるような動作については十分にリスクを説明するべきです。
一度圧潰してしまった椎体は二度と元には戻りません。
歩行に関しては体重の体重より大きい負荷が腰椎にかかります。
急性期の圧潰しやすい時期にはもちろん無理に歩行を進めないことが原則であり、そういった急性期からの継続した指導が重要だと実際に臨床で感じています。
この時期であれば、腹臥位での運動も痛みに合わせて可能でしょう。
退院後は急性期からの運動、生活指導に加えて腹臥位での運動をプラスしても良いかと思います。
運動療法
下の写真のように前鋸筋の運動と合わせて腰椎の伸展を促すと効果的です。
1.四つ這いとなる
2.前腕回内、上腕外旋位で床を押すようにする
3.押したら胸椎を丸めるように上方へ引く
<ポイント>
・上腕の外旋で肩甲骨面を上腕骨頭に合わせるように意識
・腰椎は丸めず伸展位、胸椎を丸めながら引くことを意識
まとめ
・胸腰椎移行部は構造的に圧迫骨折が好発しやすい
・急性期では圧潰予防が第一
・圧潰した椎体は元には戻らない
・時期に合わせて運動療法の難易度を設定する
おわりに
いかがでしたか?
圧迫骨折において、圧潰の予防がなにより重要であり、それを如何に予防しながら運動療法を進めていくかが鍵となります。
繰り返しますが、一度圧潰してしまうと二度と元には戻りません。
それを頭に入れて臨床に取り組んでくださいね!
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考・引用文献
赤羽根良和:理学療法ジャーナル 44巻6号 骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折に対する運動療法の意義-椎体圧潰変形の抑止効果について
オススメの書籍
Physio365
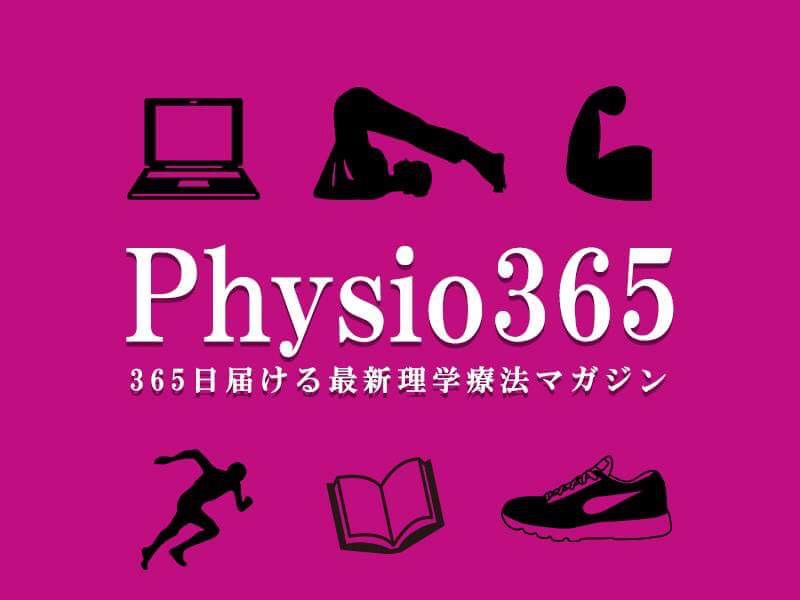
7人の個性的なセラピストによる、毎日配信の月額マガジンです。
7人がそれぞれの得意分野について、テキストや動画を用いて分かりやすく、かつ、ボリュームたっぷりでお届けしてます。
興味がある方はこちら↓
最新記事 by 松井 洸 (全て見る)
- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日
- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日
- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日
関連記事 - Related Posts -
-
2016/09/22
-
横隔膜からみた呼吸リハビリテーション
-
2018/02/26
-
頚部痛のリハビリ【頚部に負担をかけている原因を探す】
-
2017/03/16
-
股関節の可動域制限を改善するためのポイント
-
2016/08/18
-
筋膜とは?理学療法士が解説する正しい筋膜の知識
最新記事 - New Posts -
-
2019/07/03
-
足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと
-
2019/04/30
-
腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき
-
2018/12/06
-
Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開



